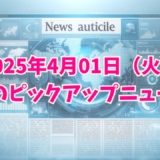この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日本列島は、その地理的特性から地震や津波といった自然災害のリスクに常に晒されています。中でも、南海トラフ沿いで発生する巨大地震は、広範囲に壊滅的な被害をもたらす可能性が指摘されており、国民の安全と安心にとって重大な懸念事項です。この度、南海トラフ地震の新たな被害想定を含む報告書が公表され、津波浸水域の拡大や甚大な死者数が改めて示されました。本稿では、この最新の報告書の内容を深く掘り下げ、その背景にある要因、そして私たちが取るべき対策について考察します。
最新報告書の概要:南海トラフ地震の新たな脅威

先日公表されたニュース記事では、南海トラフ地震による津波浸水域が従来の想定から3割拡大し、最悪の場合、死者数が30万人弱に達する可能性があると報じられています。この衝撃的な予測は、私たちの防災意識を改めて見直し、より一層の対策を講じる必要性を強く示唆しています。
報告書の特定:内閣府による最新の被害想定
このニュース記事の根拠となっているのは、内閣府の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が令和7年(2025年)3月31日に公表した報告書です。このワーキンググループは、南海トラフ巨大地震対策の検証や被害想定の見直しを進めてきた国の検討会であり、最新の科学的知見や防災対策の進捗状況を踏まえて、新たな被害想定をまとめたものです。報告書の作成には、名古屋大学の福和伸夫名誉教授が主査として深く関わっています。この報告書は、従来の被害想定から約10年が経過した社会状況の変化や、新たな地形・地盤データに基づいて見直しが行われた結果として発表されました。
津波浸水域3割拡大の根拠と範囲:近畿地方への影響
報告書によると、津波による浸水地域(深さ30cm以上)が従来の想定と比較して3割増加すると予測されています。この拡大の主な理由は、より高精度な地形データの解析が可能になったことによるものです。これにより、これまで浸水しないと考えられていた地域でも、新たに浸水のリスクが明らかになりました。
近畿地方においても、この浸水予測の変化は無視できません。特に大阪府を含む沿岸地域では、津波到達時間の早まりが指摘されています。泉佐野市では、津波到達が従来よりも4分早まるという想定が示されており、迅速な避難行動の重要性が増しています。また、大阪平野に位置するビルの地下や地下街、地下鉄といった地下空間が津波により浸水し、都市機能の中枢が麻痺する可能性も指摘されており、長期的な浸水による衛生環境の悪化も懸念されています。より詳細な大阪府全体の浸水予測については、今後の自治体によるハザードマップの作成が待たれます。
死者数30万人弱の予測要因:過去の予測との比較
今回の報告書では、最悪のケースとして全国で約29万8千人の死者数が予測されています。これは、2012年から2013年にかけての国の検討会による従来の想定(約32万3千人)と比較すると、約2万5千人ほど減少しています。この死者数減少の主な要因としては、津波避難ビルの増加や建物の耐震化の進展が挙げられています。
しかしながら、依然として30万人近い人々が犠牲になる可能性があるという予測は、その被害の甚大さを物語っています。死者数の内訳としては、津波による犠牲が約21万5千人と大部分を占めており、これは地震発生後すぐに避難する人の割合が20%と低い場合に想定されています。また、建物の倒壊による死者は約7万3千人、地震火災による死者は約9千人と推計されています。さらに、今回の報告書では初めて、災害関連死の想定も盛り込まれており、過去の震災の例から全国で2万6千人から5万2千人に上る可能性が示唆されています。南海トラフ巨大地震のような広域災害では、外部からの支援が困難になることも想定され、発災後の状況によっては災害関連死がさらに増加する恐れがあります。
「いち早い避難が命を守る」背景:避難の遅れがもたらす危険性
報告書が「いち早い避難が命を守るため必要」と強く強調している背景には、具体的なデータと分析結果があります。上記の死者数予測において、津波による死者数が避難開始の遅れによって大きく変動することが示されています。もし地震発生後、全員が直ちに避難を開始した場合、津波による死者数は大幅に減少する可能性が指摘されています。実際に、早期避難意識が高い場合(70%が避難開始)、死者数は大幅に減少すると試算されています。
避難の遅れは、津波に巻き込まれるリスクを直接的に高めます。自宅や職場、移動中に津波に遭遇する危険性はもちろん、地下街や地下鉄といった場所では浸水による甚大な被害が想定されます。特に、愛知県の沿岸部のように、地震発生から数分から数十分で高さ10メートルを超える津波が到達する可能性がある地域では、一刻も早い避難が不可欠です。冬の早朝や夕方など、人々が屋内にいる時間帯に地震が発生した場合、避難の遅れはさらに深刻な事態を招く可能性があります。
南海トラフ地震の基本情報:過去の発生履歴、メカニズム、想定規模
南海トラフ地震は、過去に何度も繰り返し発生してきた巨大地震です。記録に残る最古のものは西暦684年の白鳳地震であり、その後も約100年から150年の間隔で発生しています。直近では、1944年に昭和東南海地震(M7.9)、1946年に昭和南海地震(M8.0)が発生し、甚大な被害をもたらしました。
この地震の発生メカニズムは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む際に、プレート境界でひずみが蓄積し、限界に達したときに陸側のプレートが跳ね上がることで起こります。南海トラフは、駿河湾から日向灘沖にかけての海底に存在する溝状の地形であり、この領域が震源域となります。
想定される地震の規模は、マグニチュード8から9クラスの巨大地震であり、これは東日本大震災と同程度の規模です。震源域は非常に広範囲に及ぶ可能性があり、地震の発生パターンも同時発生や時間差発生など、多様性が考えられています。今後30年以内に発生する確率は70%から80%程度とされており、いつ発生してもおかしくない状況と言えます。
南海トラフ地震の歴史的発生記録
| 年 (西暦) | 日本の元号 | マグニチュード | 主な影響 |
|---|---|---|---|
| 684 | 白鳳 | M8.25 | 山崩れ、家屋・社寺の倒壊多数、津波で船多数沈没 |
| 887 | 仁和 | M8.25 | 京都で官舎・民家倒壊、圧死者多数、津波で死者多数 |
| 1707 | 宝永 | M8.6 | 広範囲で家屋倒壊、太平洋沿岸で津波被害、富士山噴火(約1.5ヶ月後) |
| 1854 | 安政 | M8.4 (東海) | 天竜川河口付近で最大被害、房総~土佐の沿岸に津波、翌日に南海地震発生 |
| 1854 | 安政 | M8.4 (南海) | 紀伊半島、四国沿岸で震害と津波の被害、東海地震の約30時間後に発生 |
| 1944 | 昭和 | M7.9 (東南海) | 静岡、愛知、岐阜、三重で甚大な被害、約2年後に南海地震発生 |
| 1946 | 昭和 | M8.0 (南海) | 中部地方から九州まで被害、房総半島から九州までの広い範囲に津波 |
大阪府をはじめとする沿岸地域の津波対策と今後の強化
大阪府をはじめとする沿岸地域では、南海トラフ地震による津波被害を軽減するため、様々な対策が講じられています。大阪府では、津波等の水害から市域を守るために防潮堤が整備されており、津波警報・大津波警報発表時には速やかに避難することが呼びかけられています。また、比較的平坦な地形である大阪市では、津波から身を守るために、市内の堅固な施設を津波避難施設として確保する取り組みが進められています。各自治体では、住民向けの避難計画の策定や防災訓練の実施、ハザードマップの作成なども行われています。
今回の報告書を受けて、今後さらに以下のような対策が強化される可能性があります。
強化が期待される対策
- ハード対策の強化: 防潮堤や水門の耐震化、液状化対策の推進
- ソフト対策の強化: 住民への避難行動の周知徹底、防災意識向上のための啓発活動の強化。特に、津波警報発表時の迅速な避難行動の重要性を繰り返し伝える必要があります
- 避難体制の強化: 津波避難施設のさらなる確保、避難路の整備、避難誘導体制の強化
- 情報伝達体制の強化: 緊急地震速報や津波警報の迅速かつ確実な伝達、多様な情報伝達手段の確保
- 地域防災力の向上: 自主防災組織の育成・支援、地域住民の防災訓練への参加促進
- 企業防災の推進: 事業継続計画(BCP)の策定支援、企業による防災対策の促進
政府は、今回の報告書の内容を踏まえ、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の改定を速やかに進める方針を示しており、夏頃を目途に見直しを図るとしています。
専門家や関係機関のコメント:多角的な視点からの理解
今回の報告書に関して、専門家や関係機関からは様々なコメントや分析が発表されています。名古屋大学の福和伸夫名誉教授は、「残念ながら被害そのものは大きく減じられなかったことが一番の大きな課題。何としても南海トラフ地震の被害を減らさない限り、この国の将来が非常に危ぶまれることを感じている。そろそろ本気になって対策を進めてほしい」と述べ、危機感と対策の必要性を強く訴えています。また、政府に対しては、関係機関との連携を強化し、ライフラインやインフラの強靭化、耐震化などの防災対策に引き続き取り組んでほしいとの要望を述べています。
香川県の知事は、今回の報告書を受けて、県内の震度分布や津波高、人的・物的被害の想定について、国の被害想定などを参考にしながら、香川県の地域特性を踏まえた被害想定の見直しを進めていることを明らかにしています。
これらのコメントからは、今回の報告書が専門家や関係機関に大きな影響を与え、それぞれの立場から防災対策の強化に向けて動き出している様子が伺えます。
一般の人が日頃から持つべき防災意識と準備:具体的な提言

今回の報告書の内容を踏まえ、一般の人が日頃からどのような防災意識を持ち、どのような準備をしておくべきかについて、以下に具体的な提言をまとめます。
- 住まいの安全確保: 住宅の耐震化を検討し、家具の固定を徹底しましょう
- 非常用持ち出し袋の準備: 食料、水、救急用品、懐中電灯、ラジオ、貴重品などをリュックサックに入れて、すぐに持ち出せるように準備しておきましょう
- 避難場所と避難経路の確認: 自宅や職場の周辺にある津波避難場所や避難経路を事前に確認しておきましょう。家族や地域の人たちと話し合い、避難方法や連絡手段を決めておくことも重要です
- 津波警報への意識: 地震を感じたら、津波警報・注意報が発表されていなくても、海岸や河川の近くから離れるようにしましょう。警報が発表された場合は、直ちに避難を開始してください
- 情報収集: テレビ、ラジオ、インターネットなどを活用し、地震や津波に関する正確な情報を常に把握するように心がけましょう
- 地域防災への参加: 自主防災組織の活動に積極的に参加し、地域の防災訓練にも参加して、いざという時のための行動力を高めておきましょう
- マイ・タイムラインの作成: 避難のタイミングや取るべき行動などを具体的に記した、自分自身の避難計画(マイ・タイムライン)を作成しましょう
- 災害関連死への備え: 地震発生後の生活インフラの寸断を想定し、備蓄品の量を増やす、生活用水の確保方法を検討するなど、より長期的な視点での備えも考慮しましょう
結論:知識と備えで巨大地震に立ち向かう
今回の南海トラフ地震に関する新たな報告書は、私たちが直面するリスクの大きさと、早期避難の重要性を改めて示しました。津波浸水域の拡大や依然として高い死者数の予測は、決して他人事ではありません。一人ひとりがこの報告書の内容を真摯に受け止め、日頃から防災意識を高め、具体的な準備を進めていくことが、甚大な被害を少しでも軽減し、大切な命を守るために不可欠です。過去の教訓を活かし、最新の科学的知見に基づいた対策を講じることで、私たちは来るべき巨大地震という脅威に立ち向かうことができるはずです。
南海トラフ地震被害想定比較表
| 項目 | 2012-2013年想定 | 2025年想定 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 最大死者数 | 約32万3千人 | 約29万8千人 | 約2万5千人減 |
| 建物の全壊・焼失棟数 | 約238万6千棟 | 約235万棟 | 約3万6千棟減 |
| 経済損失 | 約214兆円 | 約270兆円 | 約56兆円増 |
| 津波による死者数(早期避難率20%) | 約22万9千人 | 約21万5千人 | 約1万4千人減 |
| 地震による建物倒壊による死者数 | 約9万3千人 | 約7万3千人 | 約2万人減 |
| 地震火災による死者数 | 約1万人 | 約9千人 | 約1千人減 |
| 災害関連死(初) | – | 約2万6千人~5万2千人 | 新規に想定 |
避難シナリオ別津波死者数比較
| 避難シナリオ | 津波による死者数 | 削減率 |
|---|---|---|
| 早期避難率20%(報告書における想定) | 約21万5千人 | – |
| 地震発生後全員がすぐに避難を開始した場合 | 約10万7千5百人(概算) | 約50%削減 |
| 全員が発災後10分で避難を開始した場合 | 約7万3千人 | 約70%削減 |
 JAPAN INSIGHTS NEWS
JAPAN INSIGHTS NEWS